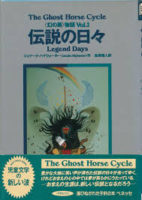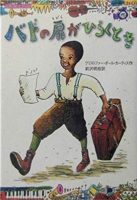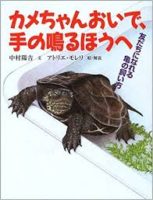石田衣良/作
新潮社
2003
トチ:今回は私とカーコさんが選書の係です。『4TEEN』と『永遠の出口』は「本の雑誌」で、たしか今年上半期のベストテンの中に入ってました。この会ではいつも一般書と児童書の境目が話題になるので、そのことを考えるには最適の2冊だと思ったのね。特に『4TEEN』は作者がテレビのインタビューで「私はいつも子どもを応援したい気持ちで作品を書いている」と言っていたことと、本について語る語り口が私の考える児童文学者の語り口そのものだったことから、今回選んでみました。さて、この『4TEEN』は、文章に透明感があるし、特に過食症の少女を書いた章など、ティーンエイジャーの恋愛を描いたもののなかでも最も美しいもののひとつではないかと思いました。ただ、一篇ずつ書いたものを後で本としてまとめたせいか、最後のほうは作者の生の声が出すぎていて、いただけなかったですが……「月島」という舞台も魅力的に、よく描けていた。好きな作品ですね。
裕:文章がすごくうまい。エイダン・チェンバーの対談相手に石田さんと交渉中らしいんだけど、何を話させるつもりなのかしら。そんなことを考えながら、私は読者に何を期待しているのかという視点で読みました。お父さんが過失致死になっちゃうでしょ。あの辺で、読者は子どもじゃなくて大人だなと思ったんですね。だから、チェンバーズと石田さんの読者は重ならないなあと思いました。子どもたちも読める文章ではあるけれど、石田さん自身が、むちゃくちゃな青春時代を過ごしてきた人だろうから、もっともっと書けるはず。でもきちんとしすぎてる。整合性がありすぎる。心の闇みたいなものが出ていないところが物足りない。整理してしまったなかの青年記という感じがしました。自転車が届いちゃうところなんかも、日本の作家のウェットさを感じました。
カーコ:スッとおもしろく読みました。それぞれ家庭環境も性格を違うけれど、4人がどこまで行っても文句なく友達だというところに、『トラベリングパンツ』(アン・ブラッシェアーズ作 大嶌双恵訳 理論社)との類似性を感じました。いいとか悪いとかではなくて、現実の子どもたちを温かく見つめて描いている感じ。でも、友達の病気とか、癌のおじさんのエピソードとか、あまりにたくさんのことが起こりすぎて、おとぎ話みたいな印象がありました。このあたり、同世代の読者はどう感じるのかなと思って、中2の息子に読ませたら、「おもしろかった。現実味がある。キャラ設定がうまい。こういうやつはいそうという気がした。自分はナオトがよかった」と言うんですね。
ペガサス:おもしろかったです。表紙もいい感じ。映画の「ウォーターボーイズ」もそうだけど、男の子の世界っておもしろくて。こんな子いそうって男の子がいて、章ごとにまとまっていて、一瞬一瞬切りとった感じはうまいんだけど、全体としての方向性は弱いかなと思いました。中学生が読めば、その世代の言葉とかが描かれているので共感をよぶと思う。いちばん成功しているのは、月島の空気感がすごくよく書かれてること。
紙魚:私は、おとぎ話でいいと思います。本を読んで、多少「こんなことってないよなあ」と思っても、少しでも「生きていくのって、悪いもんじゃない。なかなかいいもんだなあ」と思えることができれば、それがいちばん大切。この本は、まさにそういう本でした。私はもともと石田衣良さんの熱狂的なファンですが、これまでの著作のなかでも、圧倒的に好きです。石田さんの小説の登場人物には、しぜんと愛着を持ってしまうのですが、その愛着が本のなかだけにとどまらず、実生活のまわりの人たちへの愛情にひろがっていくような感じになるんです。
せいうち:かつて14歳の男の子だったぼくは、単純におもしろいというよりは身につまされて辛かったです。今となっては、なんてばかばかしいことにとらわれていたんだ、と思いますけど。子どもの世界の狭さというものが書かれていたような気がします。大人は簡単に夢をもてと言うんだけど、子どもは身の丈をわかってるんですよね。子どものとき、若いときって辛かったんだということを思い出しました。俯瞰でみると、おもしろいかもしれないけど。ぼくは単純に14歳に戻った気分で読んでしまったので、本を読んでいた電車を降りるとき、不思議な感じがしましたね。今の子に向けて書いているんだろうけど、20数年前の中学生が読んでも、普遍的にわかる部分がありました。自分が14歳のときに読んでいた本と違うのは、軽みを感じたこと。昔の本は、もっと現実から遠かったですよね。その子の将来の基本、あったらいいよねという基盤をつくる本が多かったと思います。書き手が歩み寄ったんでしょうか。これで、これからは今までとは少しずつ違う人間ができていくんだろうなあ、という寂しさもありますね。
愁童:たしかに文章はいいし、読後感はさわやかだし、印象は悪くないんですけど、直木賞と言われると、ちょと物足りない感じ。地元の読書会では、『永遠の出口』は微妙な年代差を理由に共感しない女性が多かったんだけど、『4 TEEN』は好感度が高かったですね。これは、ある意味で、女性からみた理想の少年像じゃないのかな。
紙魚:たしかに、石田衣良さんって、ホストになったらすごくもてそう。女性の感情の機微をとらえてますよね。
愁童:これって、様式美みたいな感じ。実際の男の子って、もっとどろどろしたところがあったり、理由無き反抗みたいなイライラ感の中で生きてると思うんだよね。そういうの、もてあまし気味で苦労してる母親って結構いるから、これだけさわやかにぴたりと決まった少年像を提示されると、ほっとして作品への好感度は高くなるだろうね。
紙魚:直木賞受賞後の記者会見で、記者たちが、最近多発している少年犯罪についての質問を浴びせたんですが、石田さんは、「子どもたちの力を信じたい」というようなことを言ったんですね。このところ、そういうまっとうなことを言う大人がいなかったので、とても気持ちよかったです。
せいうち:ぼくは男だからか、カッコつけようとしてもカッコわるい情けなさみたいなものはわかった。
アカシア:「月の草」の章なんかはあまりリアルだとは思わなかったんだけど、敢えてカッコつけて書いたと考えれば、これもリアルなのかもしれませんね。少年たちの若い世界観や正義感、それに今いる場所からどこにもいけない不自由さなんかはよく出てる。『スタンド・バイ・ミー』(スティーヴン・キング作 山田順子訳 新潮文庫)を思い出しましたが、4人のキャラがくっきり描かれていておもしろい。
愁童:まあ、そうだけどね。ぼくは、「歌舞伎町」っていう既成のイメージによっかかって書いてるなって感じがしてね。ちょっと…。
トチ:私は子どものころ親に黙って中野から新宿のけっこうディープな界隈に冒険に行ってたから、ここで作者が「歌舞伎町」って書いた感じ、よくわかるわ。
せいうち:ぼくの場合は、奈良市から郡山市でした。
むう:『永遠の出口』より子どもの目線に近い作品だと思う。とてもおもしろく読めました。確かにおとぎ話だし、いたって好都合にできているけれど、それでいいんじゃないかと思う。今の子どもたちの思いをすくい取っているとも思うし。最初の章で重力のことをGとか、ヒットエンドランみたいな笑顔とか、私にすればとても今風の言葉がどんどん出てきて、時代に置いてきぼりを食らったようなショックを受けたけれど、読み終わってみればそういう恐れは杞憂だった。今回の3冊のなかでは、いちばんぐちゃぐちゃと考えながら読みました。4人を主人公にして章ごとに時代を象徴するトピックが盛りこまれているのに気づいて、今度はどんなトピックだろうと考えるのも楽しみでした。もともと、ひこ・田中さんの『ごめん』(偕成社)みたいに、この年代の男の子が描かれているものが好きなんです。たしかに大人にも受け入れられるきれいなところだけを集めたからこういうかたちになっているんだろうし、「十四歳の情事」なんかいかにもカッコよすぎ。でもそれはそれでいいんじゃないかと思う。必ずしも大人が子どもの全部を理解していなければいけないとは思わないし、大人が誤解していても、それはそれで幸福な誤解というのもあって、そのなかで子どもがちゃんと育つのならいいと思うから。「ぼくたちがセックスについて話すこと」の章で、同性愛者のカズヤに対して、「だってカズヤが誰を好きになるかなんて、考えたらどうでもいいことだからね」と突き放したような優しい物言いがあって、さらに最後でカズヤがバレンタインにたくさんチョコレートをもらうという落ちも気に入った。ただし、最後の「十五歳の旅」の章はいただけない。特に最後の数ページは蛇足。こういう時代があったことをいつまでも忘れないでいようなんて、今を生きている少年たちがそんなこと言うかよ、という感じ。これでそれまでのいいイメージががらがらと崩れちゃった。なんだ、大人目線の懐古趣味じゃないかって。残念です。
羊:私は住んでいるところが月島に近いので、それがきちんと書かれていて雰囲気がよく伝わってきた。高校生だとやめて働くような出口があるけど、中学生くらいでは、そこでしか暮らせない感じはよくわかる。さわやかすぎるかもしれないけど、それでもいいかなと気持ちよく読める。この子たちには大人との接点があまりないけど、中学生くらいって、親ってそう身近に存在してなかった。友だちと「昨日、親と何回話した?」っていう話が出て、「おはよう」しか言わなかったのを思い出したこともある。さっき、歌舞伎町が意味があるかって話になったけど、同じ本を買うのでもある街に行って買うことが大事だった時代を思い出す。
ブラックペッパー:今回の3冊はどれも読みやすかったのですが、『4TEEN』は遠くから見てる感じで、あんまりひりひりするようなものは伝わってこなかった。上手すぎて、すーっといっちゃう。たまたま、テレビの「真夜中の王国」に石田衣良氏が出ていて、司会の鴻上尚史が、「この本、事実関係でちょっとまちがってるとこがありますよね」って言ったんです。「ストリップの場面で『誰も見てない』って言ってるけど、『ひとりは見てる』でしょ」って。実際はふたり見てるんですけど、石田氏は「いいんですよ。小説は生きものですから」って答えたのが、すごくよかったんですよ。不遜な感じもなく、力が抜けてて……。ゆとりある風情でした。修行時代には、1日に3冊読むことを決めていたとか、励んでいたらしいんですけど、なんだか新しい人だなあと思いました。ところで、石田衣良の名前の由来って誰か知ってますか? 本名なの? 大島弓子の『バナナブレッドのプディング』(白泉社)に「いらいらのいら」っていうのがあって、それからとったのかと。
紙魚:たしか、本名が石平(いしだいら)さんっていうんですよね。
アサギ:朝日新聞の書評で、川上弘美がほめてたでしょう。こんな文章を書く人がいるなんて信じられないというような書き方をしていたのね。私、川上弘美が好きだから、すぐにこの本読んだんです。私ね、これは大人の書いた14歳の少年像だと思ったの。だから子どもは共感するかどうか疑問だったのね。綿矢りさの『インストール』(河出書房新社)は、17歳が17歳を書いているでしょ。あれは、私には全くわからなかった。でも、この『4TEEN』の14歳は、ずっとわかりやすかった。その違いはなんだろうと考えたんだけど。たとえば『4TEEN』は、ページを開いたときの字面だけで大人が書いたと思う。あと、さっき話題になった歌舞伎町については、私にはリアリティがあったわ。子どもの行動半径は狭いからね。ブラックペッパーさんがおっしゃった「いいんですよ」っていう話について言うと、ドイツの本も細かいところは間違いだらけなのよね。紅茶と珈琲が話の途中で入れ替わっていたりね。でも編集者は、「そんなこと本質的じゃないから」っていうのね。ドイツの読者も気にしないらしいのよ。
(「子どもの本で言いたい放題」2003年9月の記録)